巨人国渡航記秘録(前編)
Chelgi・作
笛地静恵・訳
----------------------------------
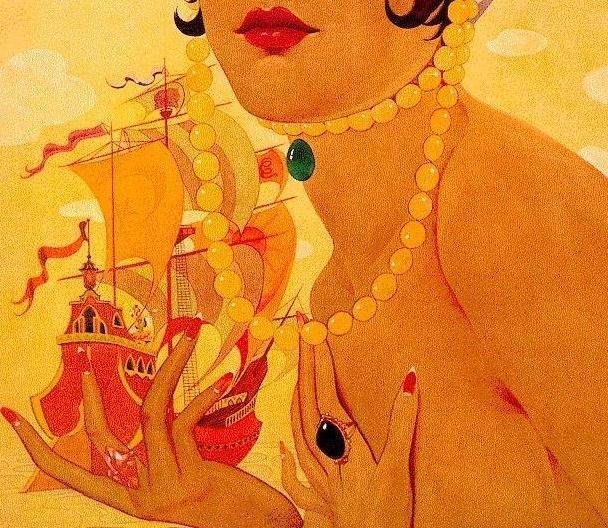
「王妃様にお仕えする女官たちの中でも、いちばん美しいのは、十六歳になったばかりの、
おてんばな少女でした。 彼女は、ときどき、私をその乳首にまたがらせてみたり、その他にも、
いろいろな悪ふざけをしたりして遊んだものでした。
この経験については、あまり詳細に、立ち入らないようにするつもりです。
読者諸賢も、そのあたりの細かな説明については、どうか筆者の心情をご推察の上で、
ご勘弁願いたいと思うのです。」
『ガリバー旅行記』
第二編 巨人国渡航記より
----------------------------------
プロローグ
まったく自然な成り行きで、ございました。
私は、それまでに王妃陛下との間に、親密な関係を築き上げておりました。
私と過ごす時間を、たいへん好まれておりました。
一週間に数回は、午後の間、私をずっと手元においておく習慣でした。
そのために、グラムダルクリッチの日課を、調整されていたのです。
おかげで、彼女は私を世話する責任から解放されて、勉学に専念することができていたのでした。
ある日の午後のことでございました。
可愛い乳母さんは、私を箱部屋の中に入れて、王妃様のお部屋にまで運んでいったのです。
室内は無人でした。 彼女は、いつものように王妃様の化粧台の上に、箱部屋を置きました。
王妃様が、お部屋にお戻りになるまでは、何があっても部屋から出ないようにと注意したのでした。
彼女は、私を一人、広大な部屋の中にに残したままで、出ていってしまいました。
いつもの光景です。 ここは眠るだけの寝室なのです。
寝台と、壁に大きな姿見の鏡があるだけの、殺風景な部屋でした。
しかし、私は、すぐにこの状況に飽きてきました。
それに、これが王妃様のお部屋を探険する、またとない機会であるとも考えていました。
すみやかに箱部屋から出ました。 待ちに待った冒険を開始しました。
1・王妃様の足元
私がまっさきに調査したいと思っていたのは、化粧台の下にある、部屋履きの牛皮のスリッパ
でした。 それほどに、気持ちを引き付けるものは、この部屋にも他にはなかったのです。
化粧台から、まず椅子の上に飛び降りました。 床に下りました。
白と黒のぶちの巨大なスリッパが、ありました。 牛の革で作られていました。
まるで広大な床の平原の上に、二頭の牛が寄り添って寝そべっているようでした。
王妃様愛用の品でした。
なぜ、これに興味があったのかと言えば、その牛が、明らかに、私の母国の牛と同じサイズで
あったからです。 彼らは、いつどのようにして、巨人たちの国にやってきたのでしょうか。
まさか私と同じように、海から流れついたとは考えられませんでした。
陸路で、この国に来たのではないでしょうか。
そうだとすると、徒歩で、この国から人間の世界に戻る道があるような気がしました。
この国の東には、巨人でも越えられない山脈があるという話を、王妃様から伺ったことがあります。
その向こう側が、普通の人間のサイズの世界なのではないでしょうか。
巨人には無理でも、牛馬ならば越えられる、一筋の細い細い道があるのかもしれません。
もしかすると、人間も辿れるかもしれないのです。
人間の世界が、たまらなく懐かしかったのです。 遥かな便りのような気がしました。
スリッパは、私の身長の二倍近く大きかったのです。
私は足を上げて、その上に登りました。表面を丹念に観察していました。
片方だけでも、数頭分の牛の皮が使われているでしょう。
王妃様の美しい御足の輪郭が、しっかりと刻印されたように、深く皮の上に残っていました。
厚い牡牛の革でした。 が、あの美しいご夫人の巨大な体重に、毎日踏み潰されていれば、
このような状態になっても当然でしよう。
彼女は、ブロンブディングナップ人の女性としては、小柄な方でしょう。
スリムな体型をしてらっしゃいます。
けれども、その身長は、二十四メートル以上にもなるのです。
体重はというと、失礼ながら五十トンは下らないでしょう。
化粧台の下の危険な冒険に、夢中になっていました。
爪先の入る内側の方まで、潜り込んでいました。
すると、そこに足の指の指紋の跡まで、発見したのでした。
そこだけが、かすかに黒光りしていました。 渦を巻いていました。
顔をよせて、仔細に観察していました。 目を懲らしていました。
そこから発散する、臭気にむせていました。
慣れてくると、不思議に不愉快なものではなかったのです。
男を酔わせる、あの麝香に近いような芳香でした。
私は、故国イングランドの港町の、娼婦達との夜を不意に思い出していました。
突然。自分が勃起していることに、気が付いたのです。
巨人の国に漂着してから、圧倒的な緊張感のために、ついぞ体験したことのない感覚でした。
女性の靴と、その臭気に勃起するなど、正常な男性としては、恥ずべきことです。
それも、雄大にして壮麗な、王妃様のような高貴な方に対して……。
誓って申し上げますが、女性の素足に、親しく接していただけの物に勃起するなど、
今までの人生で一度だってなかったのです。
自分の予想もつかない反応に、心底、当惑していました。
部屋の扉が、重々しい音を立てて開きました。
バスローブ姿の王妃様が四人の女官達を従えて、ずかずかと部屋に入ってこられました。
私は、混乱していました。 王妃様の部屋の、このような秘密の場所に隠れていることなど、
とても許されることではありませんでした。
自分が、危険な状況におかれていることを、悟っていました。
なんとかして、あの化粧台の上の、箱部屋の中に、急いで戻らなければならないのです。
王妃様と女官の方々は、真っすぐに私のいる化粧台の方向に、歩いてくるではありませんか。
化粧台の椅子が、後方に引かれていきました。 王妃様、ご自身がお座りになりました。
そして、また化粧台の正面の位置に戻されたのでした。
お召しになっていたローブの裾が割れて、舞台の幕のように、大きく広がっていました。
通常は、その下には、なにも身につけない習慣でした。
私は、すぐに王妃様が、入浴してきたばかりだということに気が付きました。
その内部から、石鹸の芳しい香と、あたたまった肌の匂いが、ほんのりと空中に漂って来た
からです。 このような早い時間帯には、珍しいことでした。
人生に、本当の絶体絶命の窮地があるとしたら、今が、その場所でした。
身長二十五メートル以上の淑女の方々四名が、その周りをぐるりと取り囲んでいる場所から、
脱出する方法があるでしょうか。
スリッパの中から、出たとします。 それぞれが、十メートル以上の長さのある、八本の脚の柱
の一本が、偶然のことから、私を踏み潰してしまうかもしれません。
五十トンを軽く越える全体重を、無造作に乗せてです。
いや、かすかに触れられただけでも、私の運命は最期となるでしょう。
もし、彼女たちの一人が、私を目の端に捉えたとします。
虫だと思って、即座に厚いスリッパの下にされるでしょう。
死刑執行は迅速で確実でした。
何度も、そのような運命に陥った生物の、苛酷な末路を見てきました。
私にできることは、小さな身体をいやがうえにも小さくして、スリッパの奥に潜り込んで震えて
いることだけでした。 王妃様から出来るかぎり、距離を取りたかったのでした。
全員が、この部屋から出ていってくれることを期待していました。 女官達は、にぎやかに笑い
さざめきながら、王妃様のお顔とおぐしの手入れを、なさっているようでした。
私は慄然としていました。
王妃様の御足が、私の方に、ずりずりと床を滑ってくることに気が付いたからです。
スリッパを探しているのでしょう。
それは、まさに巨人の足でした。
三メートル五十センチ以上の長さがあるでしょう。
親指だけでも、三十センチはあります。 清潔な真珠のような白い肌でした。
湯上がりで、ほんのりとピンク色をしていました。
私は、スリッパの中から這い出ていました。命からがら、その背後に回って隠れていました。
ローブの裾から覗いた、引き締まった細い足首でも、直径が一メートル以上はあって、
大木の幹のようでした。 頭上には、もっと巨大な膨ら脛を、仰ぐことができていました。
ローブの裾から、両脚の膝から下が、にょっきりと姿を表していたのです。
雪花石膏(アラバスター)のように、真っ白ですべすべとした肌が、光を放つようでした。
柔らかい肉で出来た柱でした。
六メートル程の上空の膝で直角におれて、バスローブの垂れ幕の中に隠れていたのでした。
私は、この途方も無く巨大ではありますけれども、完璧な左右対称の構造物の荘厳な美に
打たれていました。 神殿を礼拝しているような厳粛な気分になっていました。
王妃様とは、あれほどに長い時間を、ともに過ごしていましたのに、これほどにまじかで、
その素脚を拝見したことは一度もなかったのです。
いつもは、豪奢なドレスの下に隠れていたからでした。
二本の双生児の円柱は、スリッパと私を間に挟むようにして、頭上に聳えていました。
そして、王妃様の脚が、白と黒のぶちの牛皮のスリッパを、無造作にお履きになられたのでした。
私の脱出行は、間一髪だったのです。
今頃、彼女の爪先で、磨り潰されていたかもしれないのです。
女主人の体温に暖められたスリッパは、一段と濃厚に、あの麝香の香を発散し始めたのでした。
私は、自分が再度、不覚にも、巨人の国の厚いごわごわとした絹地のズボンの中で、
勃起していることを、認識していました。 その場所に茫然と立ち尽くしていました。
王妃様は、沐浴の後で、すっかりくつろいでいられたのでしょう。
いつもの慎ましく礼儀をわきまえた女性ならば、けしてやらないような動作をしたのでした。
膝が外側に動いていました。
自然の崇高な美の傑作である、城門の両方の柱が、さらに左右に開いていったのです。
舞台の幕であるローブは、完全に上がったのでした。 彼女の巨大な質量を持つ太腿の回廊
の奥に、禁断の女性自身という扉を、かいま見てしまったのでした。
私は、この高貴な女性に対して、自分の心の中に沸き上がってくる欲望が、信じられませんで
した。 肉体の変化も同様です。
王妃様に、お付きの若い女官たちの裸体の風景は、もう何度も見させられておりました。
そこには、恐怖と嫌悪しかなかったのです。肉体にも何の影響も、及ぼさなかったのです。
しかし、この高貴で美しく、お優しい女性の脚のあられもない光景が、イングランドを船出して
以来、かつてなかったほどに、私を激しく興奮させていたのでした。
そして、この神秘な谷間の光景は、男性自身が耐え切れる限界を越えていました。 いつの
まにか女官たちが、静かに部屋を出ていってしまっていたことにも、気が付かなかったのです。
2・王妃様の指先
王妃様の声が、やさしく私を呼んでいたのです。
「ガリバー、ガリバー、どこにいるの? 出ていらしゃい。 ガリバー」
私は、答えることも出来ませんでした。
王妃様は、箱部屋に私がいないことに気が付いたのです。
動くことも出来ませんでした。
こんな所にいたことがわかったら、私は、どうなるのでしょうか。
彼女のもっとも秘密の場所さえ、目撃してしまったのです。
それは、私の人生の最期を意味するでしょう。 不敬罪で死刑は確定でした。
いや、裁判のような手間もいりません。
王妃様が、その牛皮のスリッパで、私を踏み潰せば、すべては終わるのですから。
突然、劇場の垂れ幕のようなバスローブが、風を起こしながら、ばさっと閉じていました。
そして、両脚の柱が、ごごごごと床を鳴動させながら、移動していきました。
代わりに大きくても美しい顔が、化粧台の下の空間いっぱいに下りて来たのでした。
私たちは、しばらくの間、そうして目と目を見交わしていました。
「私は、ずうっとそうではないかと、疑っていましたよ。
箱部屋の中に、そなたがいないと、気が付いてからはね。
この部屋のどこにも、姿が見えなかったのですもの。
レミュエル・ガリバー。
私は、いつもそなたのことを、教養ある紳士として扱ってきたつもりです。
しかし、本当は、いやらしい覗き魔だったのですね。
女性のもっとも秘密な部分を、盗み見しようとするなんて……。
そなたは、あそこの眺めを、楽しんでくれたのでしょうか?」
私は、王妃様の楽しげで、明るい親しげな口調が、ほとんど信じられませんでした。
言葉自体は、私の破滅の運命を、明確に宣言していたのです。
けれども、声に秘めた調子は、からかうような陽気なものでした。
明るすぎるといっても、良いぐらいでした。
それは、今までの親密な関係よりも、さらに一歩進んだ間柄への、招待状のように感じられました。
「そなたは、あそこの眺めを、楽しんでくれたのでしょうか?」ですって?
王妃様は、私がそこにいると知っていて、あんな、はしたない行為を、されていたのでしょうか。
王妃様の声の調子は、愛する男とその罪の秘密を分け合おうとする女のものでした。
彼女は、巨大な手を私の立っている床のところにまで、差し伸べていました。
「おいで、小さな人よ。 私は、今回の小さな事件の真相を、もう少し究明したいのです」
それが、死刑執行台への片道切符であったとしても、他に、どうすることができたでしょうか?
私は、その厚い手のひらの上に登りました。
私は、オモチャのように、空中に持ち上げられていったのです。
化粧台の上の、箱部屋の脇に置かれていました。 王妃様の尋問が開始されました。
「レミュエル・ガリバー、どうしてそなたは、私の化粧台の下に、隠れていたのですか?
そなたは、もし、私の側近の女官たちの誰かに見つかれば、そのまま死罪になるとは、
考えもしなかったのですか?」
私は部分的にですが、正直に真実を述べていました。
「はい、王妃様。私は、そのことを充分に理解しておりました。
しかし、このことは、計画した上で、実行したものではないのです」
それから、私は、化粧台の上を散策している内に、そのつるつるとした表面から、
誤って転落したのだと説明しました。
「運良く、椅子の上に落ちて弾んだので、一命を取り留めたのです。
そうでなければ、首の骨を折るところでした。
なんとか、化粧台の上に戻ろうとしていると、あなた様と女官の方々が、
部屋に入って来ました。
私は、自分の失敗を恥じて、スリッパの内部に隠れておりました。
私には、あなた様の、私事を覗こうというような意図は、まったくございませんでした。」
「もし、そなたが見たものが、私の「私事」だけであったとしたら、
ここで、この話を終わらせることができるでしょう。
しかし、そなたのいた位置と、そして、現在のそなたのズボンの前の状態から
考えて、そなたが「私事」以上の、私の秘密を覗いてしまったことは確実のようですね」
彼女の巨大な手が、ふたたび私に接近してきました。
それは、なんと、私のズボンの股間に触れたのです。
指先は、私の股間の固いものの形を確認しようとするように、なおも執拗に動いていました。
彼女の指先のぬくもりが、厚い絹地を通して感じられる程でした。
敏感な指先が察知した物体を、優しく愛撫してくれていました。
力は完璧にコントロールされていました。 強すぎて痛いということもありませんでした。
絶妙をきわめていました。 私のそこを、さらに固く大きくしていったのです。
王妃様が、身を屈めているのでローブの襟元から、私の目でもその奥の乳房の谷間が
覗いていました。
そして、そこから王妃様の、成熟した女らしい湯上がりの体臭が、もわりと立ち昇っていたのでした。
「おお、レミュエル・ガリバーよ。
私は、そなたの身体のこのような状態の変化を、これまでに一度も体験したことは
ありませんでした。 このような報告も、どの女官からも、受けていません。
たとえ、そなたを、もてあそびたくて、たまらない、若い美しい女官たちを相手にしていても……。
今までただ一度も、このような変化をしたことはなかったと、聞いています。
私は、そなたには生殖能力が欠如しているのではないかと、残念に思っていたのです。
私は、なんでも知っているのですよ。
しかし、これで、そなたも、立派な一人前の男であることが、判明しました。
そして、その変化が、若い美しい女官たちではなくて、他ならぬこの私に対してであることに、
一人の女として喜びを感じていることを、正直に告白しておきたいと思っています」
「……王妃様、私は、今回の不祥事を、本当に申し訳なく思っています。
恐縮しております。
私は、あなた様を困惑させるつもりも、冒涜するつもりも、まったくございませんでした」
「小人よ。 私は、そなたが、どの程度、女性について、そして、その秘密な部分の働きに
対して、知識と経験があるのか分かりません。
……しかし、そなたが、私に対してだけ、このような反応をして、その他の女官達に対しては、
そうではなかったということを、決まり悪いこととして、謝罪する必要はまったくありません。
むしろ、誇って良いことなのですよ。
……それというのも、そなたは私の肉体を見たということだけで、反応してくれました。
その原因が、そなたを熱望している、飢えた雌ぎつねの集団のような、女官たちの性的な
いたずらではなかったということは、私には名誉の徴なのです。
私は、例の十六歳の女官のそなたに対する破廉恥な行為も、知っているのですよ。
しかし、これから、そなたと私の間におこることについては、
彼女たちは何も知ることはないでしょう」
「王妃様。 どうか、信じて頂きたいのです。 私は、あなた様の秘密については、
だれにも、どんなことも漏らすつもりは、まったくございません」
「分かりました。 小さな人よ。
たとえ、王様であろうと、これについては、何も知ることはありません。
そなたが生きていたければ、そうすることです」
それから、彼女は微笑んでいました。
私の瞳を、のぞきこむようにしていました。
巨大な両手が、私の身体の上を、親密で繊細な動作で愛撫していきました。
今までに一度も発したことのない、潤んだ声音で囁きました。
「もし、私たちが、秘め事を、ともにしたとしても……」
私は、「秘め事」という言葉に、衝撃を受けていました。
「王妃様。 そんな。 お戯れを……」
しかし、巨大な指が、私の太腿の間に有無を言わせない力で、差し込まれていました。
右手の人さし指の先で、股間を上から下に向かって、撫であげていきました。
次の瞬間です。長い爪が、私のズボンのバンドを、まるで紙で出来ている物のように、
引き裂いていったのです。
そのために、ズボンがずりおちていました。
私の股間の一物は、隆々と天を差して立ち上がっていました。
彼女は、微笑していました。指先で、優しく摘んでいました。
体格の差を考えると、彼女の指の力加減の繊細さは、驚嘆すべきものでした。
そして、ほとんど爆発しそうになるまで、それを玩んだのでした。
少女のような、くすくすという含み笑いをしていました。
脈動する男根を、愛撫してくれていました。
「そなたも、これが気に入ってくれれば良いのですが。 レミュエル・ガリバー……。
私の愛撫は、そなたのお気に召しますか?」
3・王妃様の口腔
彼女は立ち上がっていました。 化粧台から一歩、大股に下がっていました。
バスローブを肩からはらりと脱いでいきました。
白い布は足元に、雪山のように積もっていきました。
私の視界をその肉体で、いっぱいにしていきました。 生まれたばかりの姿になっていました。
乳首でさえ、私の顔ぐらいの大きさがありました。
乳房から、目を逸らすことができませんでした。
「ガリバー、私の胸は、そなたの趣味にあいますか?」
彼女は、両方の乳房を、両手で柔らかく上げたり下げたりしていました。
巨大な肉塊は、重そうに揺れていました。
私は、あまりにも大胆な行為に、衝撃を受けていました。
意識に反して、男根だけは、さっきよりも、さらに熱り立っていました。
これが、十六歳と十三歳一ヵ月という、二人の王女様の母親の身体だとは信じられない
ぐらいでした。 若い肌の張りと艶を丸々と保っていました。
「……王妃様のお胸は、私が今までに、この世で見ることができたものの中で、
もっとも美しいものでございます」
王妃様は、化粧台の方に一歩を進めました。 そのすぐ脇に、お立ちになっていました。
私を片手に掴みました。 持ち上げられていきました。
彼女は、私のゆるんだズボンを足首に丸めると、そこから引き抜きました。
化粧台の上に置きました。 荒い鼻息が、私の髪の毛をなぶって、吹き過ぎていきました。
シャツも指先に摘むと、頭から引き抜いていました。
ともに王妃陛下の命令によって仕立屋が探して来た、この国でもっとも薄い絹でありました。
イングランドならば、毛布と変わらぬ厚みがあったのですが。
完全に素裸にされていました。
私は、その姿で、彼女の手のひらの上に横たわっていました。
例によって細心の注意をこめて、彼女は私の身体を胸から腹へと、
巨人の指の先端で愛撫してくれていました。
「……そなたも、このように均整の取れた、男の身体を持っていたのですね」
官能的な囁き声でした。
「このように、可愛らしくて……。 小さな引き締まった筋肉を」
私の筋のついた腹筋を、撫でていました。
「そなたの身体は、小さくはありますけれども、本当に、男性としての完全な形をしているのですね?
まるで、人形作りの名人が、あまりにも完璧な人形を作ってしまったので、
それに命が、吹き込まれてしまったかのようですね」
彼女は、私の男のものを、特に念入りにご覧になっていました。
その間も、両脚の間の愛撫をやめなかったのです。
激しい欲望に突きたち、びくんびくんと脈打ちながら、痛い程に反り返っていました。
彼女は、直立した陰茎を、優雅に撫で上げてくれていました。
暖かくて柔らかい巨人の指の刺激が、全身を震わせていました。
「ああ、なんて可愛らしいのでしょう。 こんなに小さいのに。
複雑で。 精巧で。 完全な殿方の持ち物の形をしているなんて!
そなたは、自然の生み出した奇跡です」
「お褒め頂いて、ありがとうございます。 王妃様。
あなた様こそ、地上に下りられた女神のようにお美しい。
世界中の死すべき定めの女達を探してあるいても、
今のあなた様のように、美しい存在はありえないことでしょう」
私にも、自分が今、口に出してしゃべっている言葉が、信じられない気分でした。
「そなたが、私の身体を好いてくれていることを、とても嬉しく思いますよ。
そなたの小さな肉体こそ、とても魅力的ですよ。
なんと、良い大きさをしているのでしょうか?」
彼女は、うっとりとした目で、そういいました。
両手の中で、私が鼠一匹分ほどにも、大きくもないというように、自由自在に動かして、
上下左右から隅々まで観察したのでした。
王妃様の巨大な大きさからすれば、私など、そんなものに過ぎないということは、
わかっておりました。 遊び戯れるための、オモチャにしか過ぎなかったのです。
しばらくして、彼女は、また片方の手の窪みに、私を座らせていました。
巨人の親指が、私の胸を、そっと突いていました。
横たわるように要求されているのが、わかりました。 それに従いました。
人さし指も、親指に参加しました。 私の肉棒を、摩擦していきました。
突然、彼女は、私を目の高さに持ち上げました。
そして、少しだけ下げていきました。
最初は、私はキスをするつもりなのだろうと思っていたのです。
しかし、私の性器が彼女の唇の間に、ぱくりと挟まれていました。
王妃様の芳しい息の香がしました。 口がぱっと開きました。
良く動く舌の先端が、口の中から飛び出して来ました。
広大な濡れた唇の表面を、べろりと舐めていったのです。
巨大なうねうねと蠢くような、ピンクの肉でした。
それから、私の股間の器官を突くようにしたのです。
ヴェルベットのよう。 曲がりくねった舌の感触。
太腿の内側。 優しく舐められて。 ぐしょりと。 唾液に濡れて。
下半身まで濡らしながら。 腹部にまで、ぞろりと這い上がって。
私は、彼女の口の中の唾の匂いを嗅いでいました。
それから、私の男性自身を捉えていたのです。
官能的で、荒々しい舌の動き。 翻弄されて。
敏感で。 温暖で。 柔軟な筋肉。
勃起した男。 ぎゅっと。 強く。 押し当てられて。
私は、そこまでされても、まだ彼女が、私の全身を舐めることで、
からかっていらっしゃるのだろうと考えていました。
全身を震わせていました。 それから王妃様らしい、敏感で柔軟な繊細な神経を内蔵した舌が、
私の股間に、再度襲来していました。
巨大な蠢く肉塊の先端を、私の器官にぶつけてきたのでした。
・・・ああ、おお。 巨大な舌。 エロティックな荒々しさよ。
私の陰茎の上。 何度も。 何度も。
上に。 下に。 ぴくぴくと。 ふるわせながら。
巨大な舌。 ヴェルベットのような、ねばついた感触。
先端も、指のようにすばやく動いて。 震えながら。
彼女の舌。 腰を強く押しつけていく。 巨大な唇。
微細な皺が撚っている。 私を刺激する。
彼女は、私の股間に、情熱的なキスをする。 マンモスのようなキスの力。
勃起した陰茎。 彼女の濡れた唇の間。 吸いこまれていく。
そして、ぬるりと吐き出される。
その動きは、何回も、何回も、繰り返されて……。
私も、これが意図的な性的な行為であると、認めざるを得なかったのです。
彼女は、巨大な指の上に私を乗せたままで、その腰を唇に押し当ててくれていたのでした。
ああ、おお……。 途方も無い質量を持った、舌の肉の重みよ。
私の陰茎を、しゃぶる。 なめる。 吸う。
巨大な濡れたような唇の間で……。
・・・ああ、おお。 巨大な舌のエロティックな、荒々しさよ。
私の陰茎の上を。 何度も、何度も。
上に。 下に。 ぴくぴくと。 ふるわせながら。
私は、ほとんど射精しそうになっていました。
彼女の指は、私を乗せたままで、腰を前後に動かしてくれていました。
とても優しい動きでした。
優しい力よ。 私のペニスは、熱い唇の間に。
持続して勃起している器官も、ストローのようなものでしかないのでしょう。
それでも、私自身は快感の大波の中に、溺れ切っていたのでした。
数秒後、私はクライマックスに達していました。
エクスタシーの激動の中で、何度も何度も、王妃様の洞穴のような口の中に、
精を注ぎこんでいたのでした。
*******
巨人国渡航記秘録(前編) 了
| 投稿小説のページに行く | めくる |